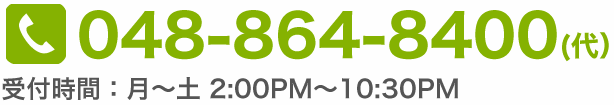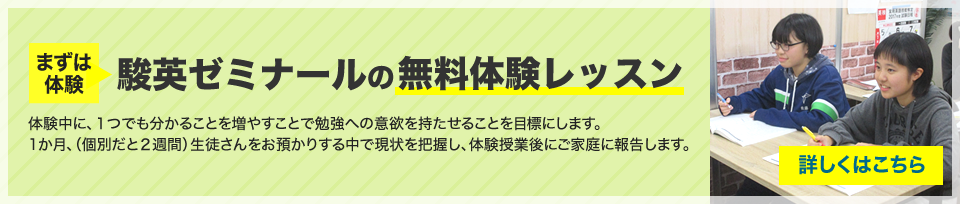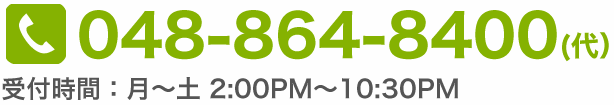先生ブログ


志望理由書で生徒が成長する
2020年11月02日 21:11
こんばんは。駿英ゼミナールの増渕です。
ちょうど10月、11月は高校3年生は推薦、AO入試の時期です。今年から推薦入試は「学校推薦型選抜」、AO入試は「総合型選抜」という名前に変わりました。
正直、名称変更はどうでも良いのですが(笑)、上記の入試において最も大切なのは「志望理由書」です。
大切というのは、もちろん合否に関わるという点もあります。これを元に面接もされますし、何を経験してきて、大学で何をするのかが詰まっているものであるからです。
しかし、やはり我々としては、合否よりも志望書を作る過程を大切にしています。巷では講師が書いてしまうような塾・予備校もあるようですが、これでは当たり前ですが全く生徒は成長しません。これを書いていく過程で、生徒が成長をするかどうかです。これって、キャリア教育ですよね。
今回は、志望理由書によって、どのようなプロセスをたどっていくかを記述したいと思います。
<A君>
具体的な方向性は決まっているが、大学で何をしたいか(=研究するか)が決まっていない。
①大学で何を研究するのですか?(WHAT)
まず、高校生の多くは、大学が研究機関であることを理解していません。何かのプログラムや環境があるということを志望理由として書いてくることが最初は多いですが、「何を研究したいのですか」と聞くと答えられないことが多いです。
そして、研究することには「課題」がつきものです。これまで明らかになっていることを再現することもありますが、現状の課題を解決するための手段が研究ですよね。そしてそれを4年間かけて研究したいという理由にもなります。
つまり、Whatですよね。
抽象的なWhatを持っている子は多いですが、具体的に何を研究するのかというWhatを考えられていないことが多いです。
②なんでそれを研究したいのですか?(WHY)
次は、Whyです。なぜそれに興味を持ったのですか?なぜそれを研究したいと思ったのか。これは当たり前ですが、誰もが気になる部分です。モチベーションですね。実はこの部分が研究課題になったりもします。
例えば、「ひとり親の生徒さんがいて、社会保障制度の課題に着目して、研究したいと思った。」というのは、納得感があります。
突然、〇〇学を学びたいという生徒がいないはずです。これまで、どのような経験や出来事と対面してきたのか、その中から必ずやりたいことが生まれているはずです。
実は、これに悩む生徒は多いです。そのときには、これまでの人生グラフを書かせます。

そうすると、このときだったとかと腑に落ちる生徒もいますし、1回だと中々出てこず、再び2回、3回書いていくと、このときだと言う出来事を発見できる生徒が多いです。
ここでは、Whyの部分が大切になります。
③手段が大学での学び(HOW)
最後はHowです。WhatやWhyはわかりました。では、その課題解決をどのようにやっていくのですか?ということです。
そこがなぜその大学を志望するのですか?というところにつながってきます。
課題解決のために、研究したい学問の第一人者の先生はおそらくいらっしゃいます。本当はコンタクトを取って、研究相談するところまでやってもらいたいです。
そうすると、アドバイスをもらえますし、強い志望動機になっていきますよね。そういった主体性も当然ながら求められていると思います。
ということで、上記の一連の作業は、自分の将来を真剣に考えるキッカケであることは間違えありません。
志望理由書を指導していながら、結局は自分が将来何をなし得ていきたいのかというところに着地していきます。
よって、きちんとこれらを言語化することで、高校生活の学びが可視化されるだろうと確信しています。
今後、彼らが生きていくのはこういった自分が経験してきたことを可視化して、何をなし得てきたのかを言語化することが当たり前ですよね。
その練習を10代のうちにしっかりと取り組んでいることに意味があると思うのです。